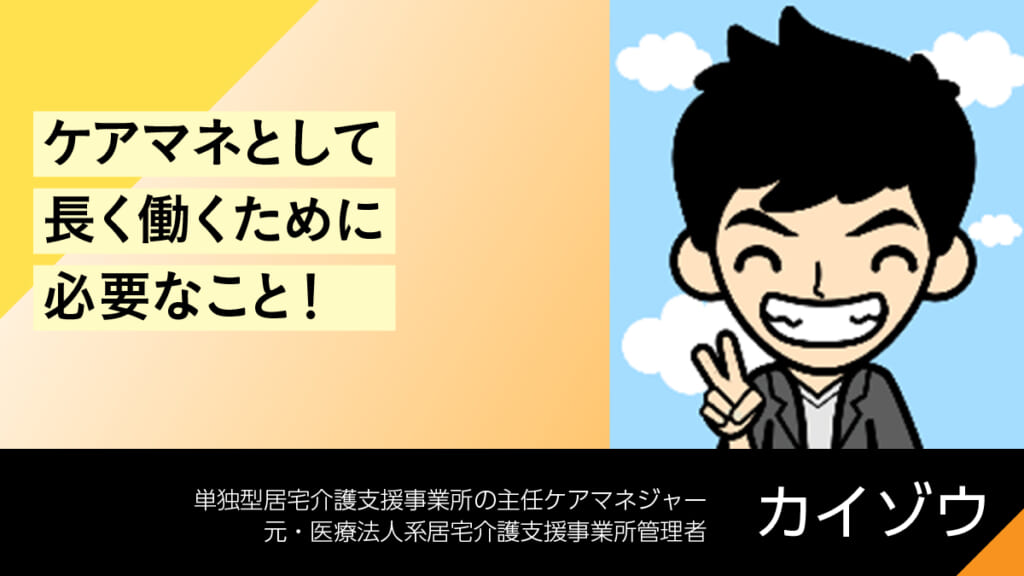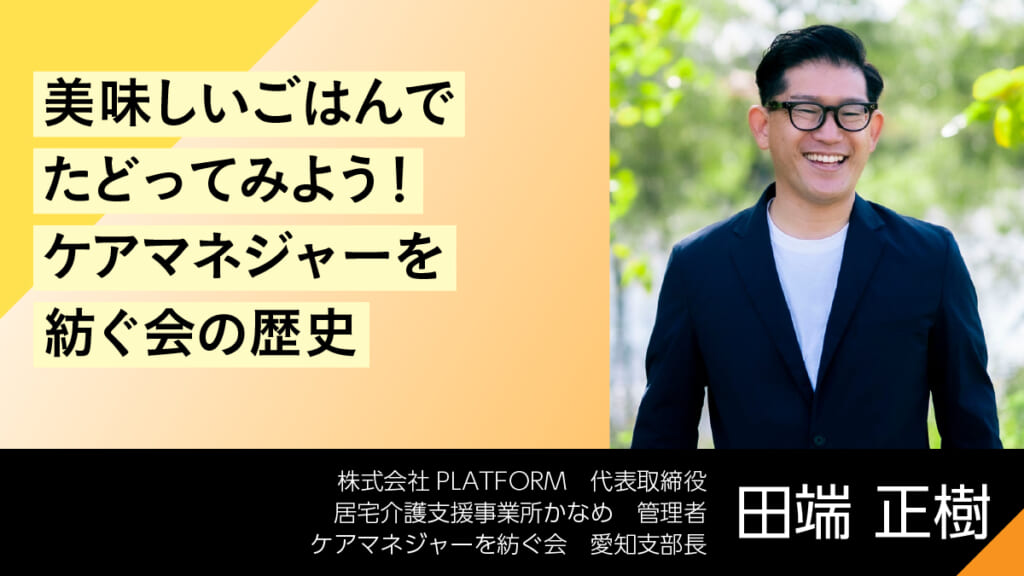介護支援専門員
産業ケアマネ
さんかくしおハッカ(高畑俊介)
ICT導入は「できる人」のためだけでなく、「不安を抱える人」に寄り添いながら進めるべき取り組みです。便利さを伝えるだけでなく、心理的な壁や組織内の空気に目を向け、誰も置き去りにしない変化を目指すことの大切さを伝えたいのです。
ICT導入と“心”のハードル
ここ数年、ケアマネジャー業務の現場でもICT化の波が確実に押し寄せています。
AIによる文章生成、音声入力、文字起こし機能など、業務効率を支えるツールは一通り揃ってきたと言っても過言ではありません。私自身、別団体でICT関連のセミナー等に関わることも多く、さまざまな現場の声に触れてきました。
とはいえ、こうした技術の導入には、大きな温度差があるのが実情です。
前向きに取り組む法人がある一方で、セキュリティや個人情報漏洩リスクへの懸念から、慎重どころか消極的な姿勢を示す事業所も少なくありません。
しかし、ここで強調したいのは「ICTのツール紹介」ではなく、「どうすれば現場でそれを“進められるか”」という視点です。
技術の解説は、私ではなく専門家に任せればよいと感じています。必要な情報は世の中にいくらでもあります。
でも、導入が進むかどうかは“人”にかかっています。そしてそれは、組織の中で、誰に目線を合わせるかで大きく変わってきます。
できる人より、「ついていけないかもしれない人」へ
ICT化の推進を考えたとき、多くの人がつい「得意な人」や「若い人」を中心に据えて考えてしまいがちです。でも、真に必要なのは、導入に躊躇している人たちの存在をどうサポートするかという視点です。
ケアマネジャーという職種は、傾向として女性の割合が多く、平均年齢も高めです。何より普段から、ありとあらゆる業務に忙殺されています。
そこに「新しいこと」が加わるということは、今やっている業務に“さらに負荷がかかる”と感じさせる要因になります。
私が事業所の支援をしてきた中でも、「ついていけないかも」「また新しいこと?」「覚えるのが大変…」といった不安の声は少なくありませんでした。
でもそれは、技術そのものに対する拒否ではないのです。
むしろ、その裏にある“心理的なハードル”こそが、本質だと思うのです。
心の奥にある「否定される不安」
アドラー心理学における「目的論」を借りるなら、ICTの導入における拒否感の根っこには、「私のやり方はもう通用しないのかもしれない」「自分の存在が無価値になるのではないか?」といった「存在の否定」への恐れがあります。
これまで真面目に、丁寧にやってきたことが、デジタルという言葉であっさり塗り替えられていくような感覚。
それは、想像以上に大きな不安や疎外感を生むものです。
だからこそ、ツールを“押しつける”のではなく、“並走する”姿勢がなにより重要です。
小さな「できた」を重ねる設計を
すべてを紙からデジタルに一気に切り替える必要はありません。
むしろ、紙を完全に奪うことは心理的な抵抗を強めます。
「まずは音声入力だけ使ってみる」
「記録の一部だけ文字起こしを試す」
こうしたグラデーションのある進め方が、心のバリアを低くします。
そして「やってみたら意外と楽だった」「あれができたから、これもやってみようかな」と、積み上げることができれば、導入は単なる業務改善ではなく、自信の回復にもつながっていきます。
その積み重ねがやがて、「変化することは怖くない」「挑戦しても、失敗しても大丈夫」と感じられる空気を生み出します。
こうした文化こそが、組織にとって最も強い土台になります。
便利なツールを使うことが目標ではなく、「チャレンジしやすい空気」をつくることを目標として進めることが大切です。
それが、ICT導入を超えて、これからのチームや職場の在り方をつくっていくのだと思います。
組織として、どこを目指すのか
ICT導入は、「できる・できない」という単純な問題ではありません。
それ以上に、「聞いてもいい」「迷っても大丈夫」「試行錯誤していい」という安心感を、チームや組織が持てるかどうかという問題があります。
できる人は、先に行っても構いません。
でも、“まだそこに立てていない人”が追いつけるように、焦らせず、寄り添い、そしてともに歩む姿勢が求められているのです。
そして、繰り返しになりますが、
ICTはあくまで「手段」であって、「目的」ではありません。
そのツールを使って、何を良くしたいのか。誰のために導入するのか。その先にどんな働き方があり、どんな利用者の支援があるのか。
そこを明確にし続けることが、組織としての軸になります。
ここはリーダーの強いメッセージが重要です。
そして、その「目的」が共有できていれば、人は動きます。
最初は恐る恐るだった一歩が、やがて自信になり、周囲を照らす光になります。
現場のICT化は、ゆっくりでもいい。
でも、確実に進める必要があります。
なぜなら、そこには「大切な人の時間」がかかっているから。
そして、「可能性」が広がっているからです。