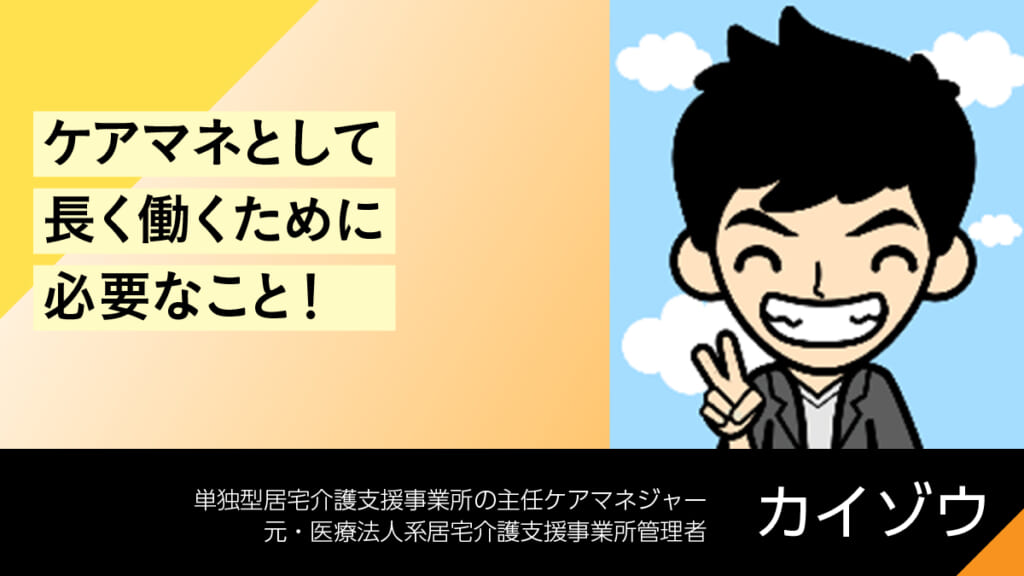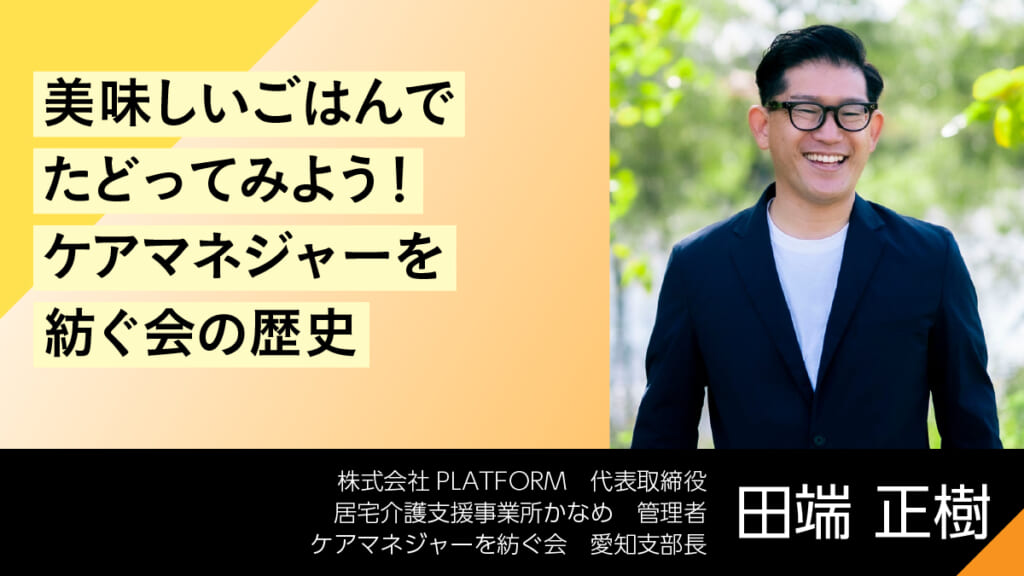株式会社 わかばケアセンター 居宅業務管理課 課長
遠藤 貴美子
めんどくさい人(ヤツ)との出会い
私と紡ぐ会さんとのお付き合いは、数年前に研修の講師依頼をいただいたところから始まりました。その時はコロナ禍真っ只中で、ウェブ研修が浸透し始めた頃でした。
研修後、私は研修をやりきったという安堵に包まれていましたが、満面の笑顔の宮﨑名誉会長から質問をいただきました。
「遠藤さんが研修の中で、ケアマネ皆が一定のレベルでなければならないと言ってたけど、なんで?」と。
心の中で「は?」と私は思いましたが、
「それは介護保険が保険という制度だからです。保険は皆に平等でなければならないからケアマネジャーによって力量に差があるのは問題なんです。」と、どこかの先生が言っていた言葉を思い出し、平静を装って返しました。
すると、「保険だとなんでケアマネ皆が一定のレベルじゃないといけないの? お医者さんだって他の仕事だって、新人っているじゃん。ケアマネだけがどうして?」と食い下がられました。
数年前のことなので、これ以上の詳細なやり取りは思い出せませんが、私はこの時に宮﨑さんのことを「めんどくさい人(ヤツ)」とものすごく思ったことだけは覚えています。
しかし、このやりとりが心にひっかかり、言葉の重みを感じるとともに、自分の中で「なんでだろう?」と考える癖がつくようになっていました。
ローカルルールに振り回される
大手の居宅介護支援事業所に所属していれば、人事異動などで全く別の区市町村(例えばA区→B区など)で勤務することで今までと書類等が変わることもあるでしょう。また、事業所が近隣の区市町村と隣接している場合にも、担当する利用者の居住地によっては同じことが考えられます。
そのような状況をすでに経験されている方もいらっしゃると思いますが、その時に必ずと言ってつきまとってくる問題が、保険者独自の決め事、ローカルルールではないでしょうか。
ローカルルールではありませんが、認定申請書、居宅サービス計画作成届出書、認定調査票の書式や記載方法が違うなんていうのはあるあるで、厚労省から発出された通知でさえも180度解釈を変えられているというケースもありました。
先にお伝えしましたが、私は宮﨑名誉会長と出会ってしまってから「なんでだろう?」と考える癖がついてしまいましたので、「厚労省から通知が出ているのに、保険者が解釈を変えるなんておかしい。ケアマネジャーを振り回さないで!」という思いで徹底的に調べ、時には介護保険課の窓口で「どうしてそのようなローカルルールなのか」という根拠の説明を求めることもありました。
ある日、そんな私を見て、もともとその事業所で仕事をしていたケアマネが言いました。
「〇〇区は、それがルールなんです」
「遠藤さんが以前に働いていた保険者のルールを押し付けられたら困ります」
決まり事だとあきらめないでほしい
そう、私はきっとそのケアマネには「めんどくさいヤツ」と思われていたことでしょう。ずっと同じルールで仕事をしてきたのに、突然、数日前に来た人が異論を主張してきたら反発したい気持ちになるのはよく理解できます。
しかも保険者にまで質問に行くなんて、目をつけられて運営指導にでも入られたらどうすんの!! 余計なことしないで!! という思いもあったかもしれませんね。
ですが、国がせっかくケアマネジャーに方向性を示してくれているのに、それに反するようなローカルルールについて「どうしてなのか」と疑問を持たないことってありなんでしょうか?
保険者が言ってるからOK? ルールだから? それって本当?
宮﨑さんの顔がグルグルと頭の中を回ります……。
本物の「めんどくさい人(ヤツ)」だと思われるために
私の願いは、そのローカルルールがケアマネジャーを苦しめるものだったら、みなさんに声を上げてほしい、ただそれだけです。
たった一言。
「改善してほしい」と。
そのためには、少し面倒で難しいと思われがちな運営基準なども読めるようにならないといけないですし、他の保険者はどのような解釈なのか等をインターネットで調べるなど理論武装をする力を身につける必要があります。
理論武装をしないで不平だけを言うとただのクレーマーとなってしまい、また違う部類のめんどくさいヤツになってしまいますから気を付けてくださいね。
そして、その理論を確認するために相手と話し合いの場を設けた時は、笑顔で友好的な態度をとることも大事です。
みなさんもよくご存知かと思いますが、話し合いというのは、挑戦的な態度で望むと絶対にうまく行きません。「ちょっと教えてほしいのですが」みたいな下手で、だけど納得しないことには何度も食い下がる……笑顔で……。
あれ? こんな人、どこかで見たことありますね?
今思えば、あの方こそ本物の「めんどくさい人(ヤツ)」だったのかもしれませんね。
今まで「めんどくさい人(ヤツ)」のことをマイナスな側面を中心に散々に言ってきましたが、ポジティブに言い換えれば勉強熱心な人です。
この勉強熱心な人が、ケアマネジャーの中にたくさん増えて、今の状況が少しでも改善されていくことを願って、私も勉強を続けていきたいと思います。